こんにちは、けいタンです。
今日はお金の話をしていきます。
今回のテーマについて
少し前から、お金を国に納める…すなわち税金について学習しています。
毎回言っていますが、なかなか税金について勉強する機会はそう多くないと思いますので、
このけいタンのブログから最低限の税金についての知識を持っていただけたらなと思います。
その中でも今回のテーマは、税金の基礎知識としての「所得税・住民税の税額の決まり方」の
2回目ということで「税負担」についてや「所得の種類」などについて考えていきます。
合わせて読むべき関連記事をチェック!
・合わせて読むべき前回の関連記事:お金と私たち~税金の基礎知識その1
↑私たちが支払っている所得税や住民税はどのくらいの額なのでしょうか?税金については大人も子ども知っておくべきことですよ!

・合わせて読むべき関連記事:お金と私たち~自分の資産を見直そう
↑自分が持っているスキルは何なのか?知っておくべき自分の人的資本を見直すことはお金を稼ぐ力の向上にもつながります!
・合わせて読むべき関連記事:お金と私たち~お金の機能を知ろう
↑銀行の金利は低いうえに、老後資金も備えないといけない今日、お金の基本知識である「お金の機能」について改めて勉強しましょう。
では早速、始めていきましょう!
復習~前回の内容のおさらい
ここでは、せっかくですので前回の投稿である「税金の基礎知識その1」の内容
をちょっとばかり復習していきましょう。

課税所得×税率で税額が算出できる
そもそも所得税・住民税は、単純に1年間に得た収入に税率をかけたものではなく、
課税所得に税率をかけて算出したものになります。
課税所得については、
会社員ならば、収入に応じて決められた給与所得控除を差し引くことができ、
個人事業主は使った経費を収入から差し引きます。
さらに事情に応じてさまざまな所得控除を行い、残った分が課税所得となります。
そして会社員は、勤務先からもらう給与所得の源泉徴収票で、収入や所得控除の内訳などを見てみましょう!
また、個人事業主に関しては、確定申告書に自分で記載して税額を計算します。
給与所得控除と所得控除と課税所得
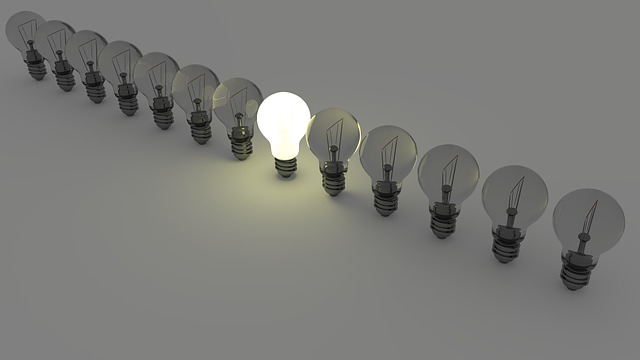
まず、1年間の収入のうち「給与所得控除(必要経費)」というものが含まれます。
この給与所得控除(必要経費)とは、会社員では速算表で求めた金額のことを、
個人事業主については、実際に使った交通費などの必要経費の合計がここにあたります。
さらには、1年間の収入から、先ほどの給与所得控除(必要経費)を引いたものが「所得」になります。
その所得に対しても、一部「所得控除」というものが含まれています。
所得控除については、配偶者控除や扶養控除、社会保険料控除などといったものがあり、
ここが最大の節税のしどころだといえます。
最終的に、所得から所得控除を差し引いたものが「課税所得」になり、
この部分に所得税や住民税がかかってきます。
なので、できるだけこの課税所得の額を減らすような控除の工夫が必要になってきます。
所得税の算出方法
所得税には、課税所得が多いほど税率が高くなる「累進課税」という仕組みがあります。
そして、「所得税額=課税所得額×税率-控除額」
これが、所得税の算出方法です。
つまり、税額を減らすためには、課税所得額を減らす(控除額を増やす)工夫が必要になります。
ここまでで、前回の内容「税金の基礎知識その1」の復習を終わりとします。
ということで、ここからが今回の本題になります。(ちょっと前回の復習が長くなったけど…笑)
では、次の項目から「税負担」について考えていきましょう。
経済的に大変な人ほど税負担は軽くなる

いろんな種類の納税者がいる
この人類社会には多くの納税者がいます。
だって、物を買うにせよ税金はかかる(消費税)し、頑張って働いて収入を得ても、
そこから一部税金を払わないといけない(所得税)…といったように
いろんな種類の税金を私たちは支払っているのです。
つまり、私たちのほとんどが納税者なのです。
しかしながら、単に納税者といってもさまざまなタイプの納税者がいますよね。
最も単純で分かりやすい例が、富裕層と低所得者の支払っている納税額の差です。
また、ある程度の収入はあっても、家族が多くて生活費がかさむという人・家庭もあるでしょう。
そのように、納税者といってもいろんな種類の納税者がいるので、
それぞれの事情に配慮した税負担の仕組みになっています。
同じ年収でも家族構成が異なると…
では、具体例として次の家族ケースを想定しましょう
- A:父・母・小学生1人
- B:父・母・小学生1人・中学生1人・高校生1人・大学生1人
※ともに父(夫)は会社員で、母(妻)は専業主婦としています
この場合に、同じ年収(ここでは年収600万円とします)でも
家族構成の異なる家族の税額(所得税)を比べてみると、
- A→所得税16.1万円
- B→所得税7.9万円
といったようにかなり差がでできます。…ていうか倍以上違いますね!
では、これはなぜでしょうか?
所得控除と税金の三原則
先ほどにもいいましたが、それぞれの家庭の事情によっては所得控除があります。
例えば、扶養家族がいる場合は所得から一定額を差し引ける「扶養控除」があります。
その他にもいくつかの控除があり、控除額が増えると課税所得が減るので、
税額も安くなるというわけです。
また、そもそも税金は「公平の原則」「中立の原則」「簡素の原則」という三原則に基づいています。
例えば、「公平の原則」とは、経済力が同等の人には等しい負担を求め、
経済力のある人にはより大きな負担を求めるというものです。
所得は全部で10種類存在する
収入が何から得られたものかによって、以下のような10種類に分けて所得を計算します。

給与所得・事業所得・不動産所得・譲渡所得・雑所得
- 給料をもらった!…「給与所得=収入金額-給与所得控除額」
→勤務先からもらう給料、賞与など - 個人事業の収入で生活している!…「事業所得=収入金額-必要経費」
→小売業、農業、フリーライターの人などの収入 - 土地を貸した!…「不動産所得=収入金額-必要経費」
→土地や建物を貸し付けるなどして得た収入 - 資産を売った!…「譲渡所得=収入金額-(取得費+譲渡費用)-50万円」
→不動産、株式、株式投資信託、金地金、ゴルフ会員権など - 公的年金や原稿料が入った!…「雑所得=収入金額-必要経費(公的年金等控除額)」
→公的年金、企業年金、生命保険の個人年金保険、または本業ではない人が受け取る原稿料など、他の9種類の所得に当てはまらない所得
利子所得・配当所得・山林所得・退職所得・一時所得
- 預金の利子が入った!…「利子所得=収入金額」
→預貯金や債券の利子 - 株式の配当金が入った!…「配当所得=収入金額」
→株式投資信託の分配金もこれにあたる - 山林を売った!…「山林所得=収入金額-必要経費-特別控除(最高50万円)」
→山林を伐採して売ったことなどによる所得 - 退職金が入った!…「退職所得=(収入金額-退職所得控除)×1/2」
→勤務先からの一時払いの退職給付や確定拠出年金の一時金受け取りなど - 生命保険の満期金が入った!…「一時所得=収入金額-そのために払った費用-特別控除」
→生命保険の満期保険金(受取人と保険料負担が同じ)、賞金、競馬の払戻金など
まとめ~税金についてもっと知ろう!
いかがだったでしょうか。
それでは最後に、今回のまとめをして終わりにしましょう。
覚えておくべき税負担と所得に関する6つの事項
- 人類社会には多くの納税者がいる(私たちのほとんどが納税者なのである)
→消費税や所得税、住民税などいろんな種類の税金を私たちは支払っている - しかし、納税者といってもさまざまなタイプの納税者がいる
→それぞれの事情に配慮した税負担の仕組みになっている - 同じ年収でも家族構成が異なると、納める税金の額(所得税など)が異なる
→所得控除や扶養控除などといった、いくつかの控除があり、控除額が増えると課税所得が減るので、税額も安くなる - 税金は「公平の原則」「中立の原則」「簡素の原則」という三原則に基づいている
- 所得は全部で10種類存在する
→給与所得・事業所得・不動産所得・譲渡所得・雑所得・利子所得・配当所得・山林所得・
退職所得・一時所得
いいね!とシェアによるこのブログの拡散をお願いします!
最期に、今回の内容で少しでも面白い・タメになると感じてくれたら嬉しいです。
そして、
面白い・タメになると思った方は、いいね!とシェアによるこのブログの拡散をお願いします。
タメになるコンテンツ作成の大きな大きなモチベーションとなります。
それでは、最後まで見ていただきありがとうございました。
そして明日の投稿もお楽しみに。けいタン
※過去の投稿一覧(ブログ)
合わせて読むべき関連記事をチェック!
・合わせて読むべき前回の関連記事:お金と私たち~税金の基礎知識その1
↑私たちが支払っている所得税や住民税はどのくらいの額なのでしょうか?税金については大人も子ども知っておくべきことですよ!

・合わせて読むべき関連記事:お金と私たち~自分の資産を見直そう
↑自分が持っているスキルは何なのか?知っておくべき自分の人的資本を見直すことはお金を稼ぐ力の向上にもつながります!
・合わせて読むべき関連記事:お金と私たち~お金の機能を知ろう
↑銀行の金利は低いうえに、老後資金も備えないといけない今日、お金の基本知識である「お金の機能」について改めて勉強しましょう。


コメント