こんにちは、けいタンです。
今回は20回目となる日本史のことについて話していきます。
今回のテーマについて
今回取り上げるテーマは、飛鳥時代の次である奈良時代の政治や宗教について
「南都六宗の僧である道鏡が誘発した天皇制崩壊の危機」という内容について見ていくことにしましょう。
ひとりの僧が天皇制を揺るがした…そんなことがあるのか?!
と思ってしまうような今回のテーマですが、
なかなか面白い内容であるので、早速ですが説明していきます。
合わせて読むべき関連記事をチェック!
・合わせて読むべき前回の関連記事:日本史~聖武天皇と大仏造立
↑疫病や権力争いが行われ、社会全体に不安が広がっていた奈良時代に聖武天皇が行ったことは大仏を造立することでした。…その真意とは何でしょうか?
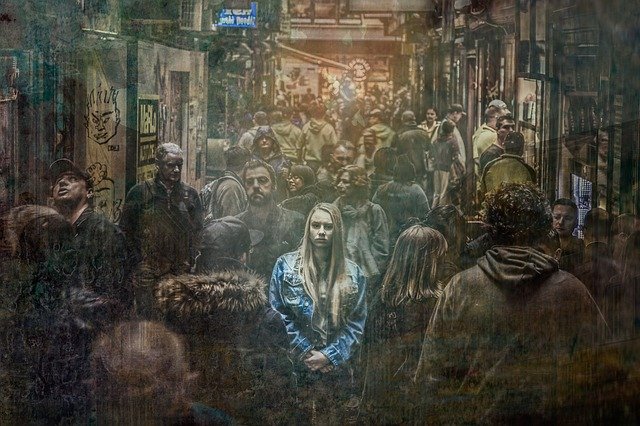
・合わせて読むべき関連記事:日本史~三つ巴の東アジア情勢
↑中国と朝鮮半島と倭国(日本)の3か国の関係性はとっても面白いですよ!そこで今回は、その当時の外交についてちょっとだけ覗いてみましょう!
・合わせて読むべき関連記事:日本史~意外と知らない縄文時代の生活
↑縄文人の生活はどのようなものだったのでしょうか?貝塚や竪穴住居から分かる意外と知らなくて、でもすごい縄文人の生活に目を向けましょう!
今回のテーマに対する結論
まずは、今回のテーマの結論から見て学びを深めていくことにしましょう。
僧が天皇制を揺すことができた背景として考えられることは、
仏教と天皇の深いつながりは、豪族だけではなく僧侶の政治介入も引き起こす結果となった、
ということです。
では、このことについて次の項目から詳しく見ていくことにしましょう。
道鏡が皇位はく奪を目論む
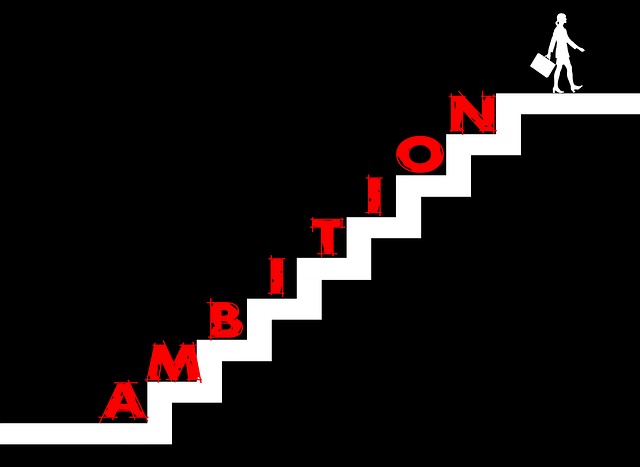
天皇に寵愛された僧
大仏造立から10数年後、聖武天皇の娘である孝謙天皇(称徳天皇)に寵愛された
僧である道鏡は、天皇の威光を盾に実権を握るようになってきました。
今風に言えば、上司に胡麻をすって機嫌をうまく獲り、
(あまり成果は良くないのに)昇進する部下のようなものでしょうか…。
まあ、それはともかく、とにかく道鏡は天皇である孝謙天皇(称徳天皇)に目立つ存在となり、
権力を得るようになっていったというわけです。
それに対して、太政大臣である恵美押勝(えみのおしかつ)は軍事力をもって権力奪取を図るも
失敗に終わってしまいました。
ちなみに、恵美押勝については前回の投稿で説明していますので、是非ご参考に。
※参考記事:「日本史~聖武天皇と大仏造立」
↑聖武天皇を襲う社会不安や、それに伴って聖武天皇が仏法に国家鎮護を願うことについてまとめています!
宇佐八幡宮神託事件
では、道鏡の気になるその後について見ていきましょう。
道鏡はその後、太政大臣禅師を経て法王にまで上り詰め、
769年に宇佐八幡宮(うさはちまんぐう)が「道鏡を皇位につかせれば天下安泰」と
神託を下したとして、皇位をも奪おうとしたのです。
なんか道鏡ってよくよく考えると、権力にまみれている点で今の国のトップと似ていますね(笑)。
そういう意味でも、人間…権力とか欲とか金などが絡んでいくと怖いものですね(笑)。
このように、天皇制を揺るがした宇佐八幡宮神託事件の結末は、
和気清麻呂(わけのきよまろ)という人物が別の神託を奏上したことで道鏡の天皇即位は阻止され、
道鏡は下野薬師寺(しもつけやくしじ)に流刑(=左遷)となったのです。
政治と結びついた南都六宗

法相宗と南都
では、もうすこしだけ道鏡について話していきます。
道鏡は、もとは法相宗の一学僧でありました。
法相宗というのは、653年に唐へと渡った道昭(どうしょう)が、
帰国後、法興寺(飛鳥寺)において広めた宗派で、
のちに藤原不比等によって興福寺が創設され隆盛を極めたものです。
平城京(南都)には、この法相宗のほかに、華厳経を最高の経典とする華厳宗、
渡来層である鑑真が広めた律宗、
そして、三論宗・具舎宗(くしゃ)・成実宗があり、6つの宗派を合わせて南都六宗と呼ぶのです。
政治と仏教のかかわりが強くなったワケ
いずれも経典の研究をはじめとする学研の場といった色彩が強かったのですが、
仏教による国家鎮護政策で国の庇護のもとにあったため、政治との関わりも根強くなりました。
まとめ~権力が一個人に集中しすぎると危険かも!
いかがだったでしょうか。
それでは今回のまとめを行っていきます。
確認しておくべき道鏡と南都六宗に関する5つのこと
- 聖武天皇の娘である孝謙天皇(称徳天皇)に寵愛された僧である道鏡は、天皇の威光を盾に実権を握るようになった
→これに対して、太政大臣である恵美押勝は軍事力をもって権力奪取を図るも失敗に終わる - 道鏡はその後、太政大臣禅師を経て法王にまで上り詰め、769年に宇佐八幡宮が「道鏡を皇位につかせれば天下安泰」と神託を下したとして、皇位をも奪おうとした
- 天皇制を揺るがした宇佐八幡宮神託事件の結末は、和気清麻呂が別の神託を奏上したことで道鏡の天皇即位は阻止され、道鏡は下野薬師寺に流刑となった
- 平城京(南都)には、法相宗のほかに、華厳宗、律宗、三論宗、具舎宗、成実宗がある
→南都六宗 - いずれも経典の研究をはじめとする学研の場といった色彩が強かったが、仏教による国家鎮護政策で国の庇護のもとにあったため、政治との関わりも根強くなった
いいね!とシェアによるこのブログの拡散をお願いします!
まあなんとなくでいいので今回の内容で少しでも面白い・タメになると感じてくれたら嬉しいです。
いや、そう感じてください!(笑)
そして、
面白い・タメになると思った方は、いいね!とシェアによるこのブログの拡散をお願いします。
タメになるコンテンツ作成の大きな大きなモチベーションとなります。
それでは今日はここまでとします。最後まで見ていただきありがとうございました。
では、またお会いしましょう。けいタン
※過去の投稿一覧(ブログ)
合わせて読むべき関連記事をチェック!
・合わせて読むべき前回の関連記事:日本史~聖武天皇と大仏造立
↑疫病や権力争いが行われ、社会全体に不安が広がっていた奈良時代に聖武天皇が行ったことは大仏を造立することでした。…その真意とは何でしょうか?

・合わせて読むべき関連記事:日本史~三つ巴の東アジア情勢
↑中国と朝鮮半島と倭国(日本)の3か国の関係性はとっても面白いですよ!そこで今回は、その当時の外交についてちょっとだけ覗いてみましょう!
・合わせて読むべき関連記事:日本史~意外と知らない縄文時代の生活
↑縄文人の生活はどのようなものだったのでしょうか?貝塚や竪穴住居から分かる意外と知らなくて、でもすごい縄文人の生活に目を向けましょう!


コメント